
こだま
読んでいて惚れ惚れする。主婦であるこだまが書いた処女作『夫のちんぽが入らない』は、その切り口もさることながら、流れるようなテンポのいい文章があまりに気持ちよく、いつまでもその文を読んでいたくなる。この人に黒いものを「白」と書かれたら、信じてしまうかもしれない。それくらい高い文章力。まさに、天才。
同時に彼女は非常にすぐれた観察者でもある。『夫のちんぽが入らない』は、夫のちんぽは入らないのに、ネットで知り合ったどうでもいい男性のちんぽはすんなり入ってしまう、そんな事実を描いた私小説だ。心は繋がっているのに体はつながらない。そんな悲哀を、その心地いい文章でどこかコミカルに切り取り、発売から2017年12月までに13万部を発行している。
それから約1年。デビュー2作目となるのが『ここは、おしまいの地』である。この本の中では、家族、職場、これまで経験してきた著者の半生が、その観察眼と文章力で描かれている。引越し業者でさえ「これは最強っすね」と鼻を押さえながら言ってくる「臭すぎる新居」=“くせえ家”、集落では周囲から怖がられ人を意のままに動かす「雷おばさん」=母親、など、何もない集落に生まれたこだまの人生を切り取った20篇。作者であるこだまにその背景について話を訊いた。
インタヴュー&文:西澤裕郎
ひたすら自分に向けて書くようになりました
──前作『夫のちんぽが入らない』を読んで、その内容もさることながら、テンポがよく淀みない文章に読む手が止まりませんでした。なんでこんな文章を書けるんだろうと嫉妬すら覚えたんですけれど、いつから自覚的に文章を書き始めたんでしょう。
こだま:はじまりは小学生の頃なんですけど、友達がいなかったので、友達に向けるかのようにひたすら日記を毎日書いていたんです。夜、寝る前に書く日記が1日の中で1番の楽しみで。日記を書くために1日をがんばっていました。その日記は誰に見せるわけでもないんですけど(笑)。
──言ってみれば、日記に書くネタを探しながら生活していたみたいな?
こだま:そうですね。「あ、これ日記に書こう」と思いながら小学生の頃は過ごしていて。おもしろいことが起こっても、言う相手もいないので日記では話しかけるように書いていたんです。「こういうことがあったよ」っていう話し口調で。
──イヤな出来事があっても「ネタになるぞ!!」的な気持ちもあったのかなと。
こだま:読み返してみると、そうやって書いていますよね。日記はイラスト付きで、「こんな嫌なことがあった」って書いていました。人の輪の中に入っていけない性格でもあったので、外から見たクラスの人の様子を日記に書いていて。それが募ってブログになっていただけで、やっていることは変わらないんですよね。

こだま『ここは、おしまいの地』
──毎日観察していたら、クラスメイトとしゃべりたくなるような気もしますけど。
こだま:本の中にも書いたんですけど、小中高と赤面症がひどくて、人とまともに話せなかったんですね。だから自分から話しかけようという気持ちには一切ならなくて。ますます自分の殻にこもって、ひたすら自分に向けて書くようになりました。
──そうやって日記に書くことで気持ちが楽になったと。
こだま:楽にもなったし、なによりも書くのが楽しかったんですよね。
──憧れの作家さんがいて、その文章を参考しているなんてことはないんですか?
こだま:本をよく読むようになったのは中学に入ってからです。学校の図書室で太宰治の本を借りて読んでいました。告白するかのように書かれた文章がとても好きで、自分にとって身近に感じられる作家だったんです。
──日記からブログに移行したことで、不特定多数の人がこだまさんの文章を読む可能性がでてきたわけですけど、そこに抵抗はなかったんですか?
こだま:知らない人だけが読んでくれるのが、自分にぴったりだったんですよね。日記はひたすら自分しか読まないし読み返さないけど、ブログは全然知らない人が自分が書いたものを読んでくれる。それがすごく好きで。知り合いには読んでもらいたくなかったので、読んでくれる人がいれば読んでくださいくらいの感じで。
このセリフを書きたかったというのは、かなりあります
──『ここは、おしまいの地』に「私の守り神」という話があります。入院しているこだまさんを訪ねてきた田舎のお母さんに「無印良品のパンツを買ってきてほしい」と頼んだけれど、無地のパンツを間違えて買ってきてしまった。同じ病室のおばさんたちに笑われる中、お母さんはレシートを握りしめ「交換してもらって来るね」と売店に向かう。その背中をみて涙が溢れるという話ですが、そういった哀しさもこの本には散りばめられています。そういう気持ちをどうして忘れずに文章にできるんでしょう。
こだま:入院していたとき、毎日日記を書いていたんですよ。メモ帳を持って行って、あったことや自分の思ったことをひたすら書いていた。母の無印事件で悲しそうな顔をしたのも、その日記にわっと書いていたんです。エッセイとして書くときに、その頃のノートを見ながら書きました。そのときどきで生まれた強い感情は、書いておかないと忘れちゃうんですよね。だから、日記じゃなくても「こういうことがあった」ってスマホにメモ程度には残しておくようにしていて。何かを書くときに、そこに残していたエピソードを入れたりしています。
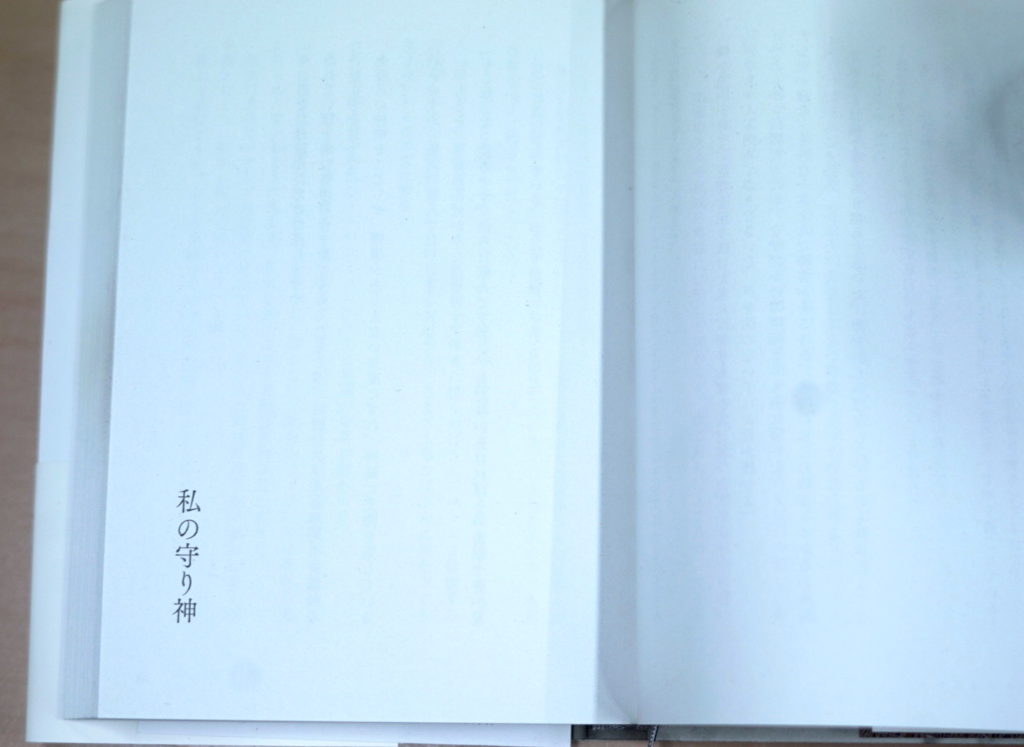
──人生の中で生まれるたくさんの感情のなかで、『ここは、おしまいの地』で描かれている話は、どのようにピックアップされていったものなんでしょう。
こだま:連載自体に大きなテーマがあったわけではなく、書けるものを自由に書かせていただいていました。生まれ育った集落のこと、そこで起きた奇妙な現象、個性の強すぎる人々、そして闘病。過去の壮絶体験をフル活用させつつ、淡々とテンポよく書くことを心掛けました。「川本、またおまえか」という話は、十数年に及ぶ川本くんへの想いと自分の抱えるコンプレックスについて書いたもので、一番思い入れのある作品です。
──小学1年生の図工の時間をきっかけに、こだまさんの痣とほくろをからかったり、なにかとコンプレックスを刺激するような存在だった川本くんに、大学生時代、たまたま改札で遭遇します。久しぶりに会った川本くんが、こだまさんに聞こえているとは知らずに発する言葉の余韻が、なんとも言えない気持ちになる。これも小説のような出来事ですよね。
こだま:大学時代に駅で偶然再会したというドラマみたいな出来事がずっと忘れられなくて。この話をいつか書こうと思い、ラストだけは決めていたんです。再会していなければ、コンプレックスをからかわれていた日々を思い起こすこともなかったですね。
──「金髪の豚」もすごい話ですよね。『ごくせん』さながらの荒れた中学で100キロ以上ある金髪のヤンキーに「付き合おう」と言われる。こだまさんも付き合ってしまうというのがおもしろい(笑)。
こだま:私は受け身であるのと断れない性格なので、たまたまこのときは相手がヤンキーだったという。そこからはじまった話ですね。
──川本くんのときとシチュエーションは違いますが、金髪の豚にも大学生になり再会します。そこで全力で走って逃げるという選択をして文章は終わっていますけど、無事に逃げ切ったのか気になるところです(笑)。
こだま:逃げ切りました(笑)。それ以降、顔を見ていません。帰省の際は近づいてくるエンジン音にかなり敏感になりました。
──そういう日常の出来事も書きながら、本質をついたような言葉もところどころに出てきます。「雷おばさんの晩年」という話では、子供たちから恐れられていたお母さんが、肺炎になりかけたこだまさんを連れて都会のお医者さんに行ったとき、お医者さんから一括される場面がでてきます。そこで描かれている言葉が印象的で、「集落では周囲から怖がられ、人を意のままに動かす「雷おばさん」も、一歩外に出ると力を持たないただの田舎のおばさんなのだ」と。
こだま:このセリフを書きたかったというのは、かなりあります。閉ざされた集落における母の立場しか見えてなかったんですけど、一歩外に出たら、ただのおばさんだったというのを知った瞬間ですね。
何かの役に立つ話ではないんですよね
──こだまさんと一緒に同人誌『なし水』を制作されていた爪切男さんも、同タイミングで、私小説『死にたい夜にかぎって』を上梓されました。爪さんの文章は、書く対象へのやさしさと謙虚さが通底しています。それに対して、こだまさんの文章はズバっと直球で本質を突くような印象があります。
こだま:爪さんは生き別れたお母さんへの想いが根底にあり、まわりと深く関わりながら生きてきた人だと思う。行間から愛情が溢れていますよね。私は人と接することを怖れて距離を置き、常に外側から見てしまう。だから観察者のような書き方になっているのかもしれません。「一歩外に出ると~」も、観察している書き方ですよね。
「人生の喜怒哀楽すべてがショー」文学フリマ発“野良の偉才”爪切男デビュー作を語る
──お母さんのことというより、他人のことみたいですもんね。
こだま:自分と母との関係じゃなくて一歩退いて見たものを書いています。自分は外れたところから見ているんだなと、爪さんとの関係を聞きながら思いました。
──自分が体験している出来事だけど、空中からもう1人のこだまさんが俯瞰して見ているような感じというか。
こだま:なるべく入り込まないように淡々と書いています。「親が好き」とか、そういうストレートな感情は持ってなかったし、あまり書きたいとも思いません。たとえ好きだとしても「嫌いではない」と、ひねくれた書き方をしてしまう。照れ臭いから一歩引いた目線で書いてしまうんだと思います。
──「穂先メンマの墓の下で」では、妹さんをレッドカーペットの階段から蹴り落としたという話があります。
こだま:自分で書きながら、めちゃくちゃひどいことをしているなと思いました。こどもの単なる好奇心ではあるんですよね。ここから落ちたらどうなるんだろうっていう。
──僕にも妹がいたので、そういう気持ちはわからなくないんですよ。その出来事を誰にも見られない前提で日記に書いているのと、誰かに見られるかもしれないブログに書くというのでは、やっぱり意識は違うのかなと思うんですね。
こだま:形は変わりましたけど、やっている本質は同じなんですよ。日記を書いて誰にも見せなかった時期と、家族には言わずに書き続けて全然知らない人に読んでもらっている現在。ブログのときと感覚は同じですね。
──『夫のちんぽが入らない』にしても『ここは、おしまいの地』にしても、実際かなりの反響があると思うんですけど、そういう現状をどう捉えていますか。
こだま:どちらの作品も何かの役に立つ話ではないんですよね。友達のいないおばさんが壁に向かってひたすら話しているような本。だから、読んでもらえるだけで奇跡だと思ってます。「自分も同じような思いをした」「誰にも言えなかったことを言葉にしてもらえた」という感想も多かったです。書いてある体験は特殊かもしれないけど、読み手が普遍的な部分を掬い取ってくれているのだと思います。
──『夫のちんぽが入らない』では、1番好きな人と心は繋がっているのに体が繋がらない哀しさが描かれていました。表層的な体験だけではなく、こだまさんの文章によって共感できる物語に昇華され、共感を呼んだんじゃないかなと。
こだま:入らないっていう直接的な体験じゃなくても、例えば性的少数者の方からも「これは自分の友達じゃないか」とか読んでくださって感想をくれましたね。
──物語を通してこうあるべきだって訴えているわけじゃないですもんね。
こだま:なるべく書いたことが読んだ人への押し付けにならないように、自分はこうですって話にとどめているんですよね。あまり主語を大きくしないってことは決めていて。「ただの自分の体験」ですという収め方をしていきたいんです。
自分のことを書いている作品が好き
──それにしても、かなり特殊な体験をされているというか(笑)。『夫のちんぽが入らない』に登場した「山に登って目の前でオナニーをするおじさん」の話は衝撃的でした。もしかしたら、みんなそういう変な経験しているのかもしれないと思うようにもなりました(笑)。
こだま:他の人に言わないだけで、こういうおかしなことを体験しているのかもしれないですね。
──友人に尋ねても絶対に言わないでしょうしね。
こだま:私もそういう感覚で、知っている人には言いたくないんですよね。
──他のインタヴューでも触れられていますけど、ここまで話題になったら、旦那さんや親族にもバレれているんじゃないかと思うんですけど。
こだま:私の住む田舎ですら本が売られているので、親族も表紙くらいは目にしたことがあると思います。本当は気づいているけど、言いにくくて黙っているのかもしれない。もうこんなことやめなさいって言われる日が来るかもしれません。だから、毎回これが最後の作品になっても後悔しないよう書いているんです。そうすると、どんどん過激なことも書き始めちゃうんですよね(笑)。最後ならここまで書いちゃおう! とか。これをずっと1年2年続けてきた感じです。
──じゃあ、まだまだ書ききれないくらいエピソードがあるってことですか?
こだま:いえ、もうけっこう限界です(笑)。大きなことはだいたい書いているので、身の回りの小さなことを拾い上げて書いていたり。次は小説を書いていこうと思っています。
──小説も楽しみですね! こだまさん自身、自分の作風に影響を及ぼしているものがあるとしたら、なんだと思いますか?
こだま:太宰治もそうですけど、自分のことを書いている作品が好きなんですよね。エッセイや私小説など、そういうものばかり読んできました。その中でも、ちょっとしたおもしろさがあるような作品ばかりですね。ただ、自分がそれらの作品のように書こうとは一度も思ったことはなくて。私は本当に運がよかったというか、たまたま同人誌から繋がっていっただけで。いまだにこんなことしていていいのかと迷いながら書いている状態です。
──いまも迷いがあるんですか?
こだま:「作家」という心境ではないんですよね。普段は、ただのひきこもりのような生活を送っているので。
たまに不吉なことが起きればいいです(笑)
──これも本に出てきますけど、1年近く“くせえ家”で生活されていたというのも想像力をかき立てらるものでした。くさすぎるのを食いしばって耐えた結果、奥歯が欠けたという話には笑いました(笑)。
こだま:これも書くっていう楽しみがなければ、ただのつらい出来事のはずなんですよ。こうやって本に書けたから、ちょっとおかしな話として済んでいますけど、ひたすら辛かったです。
──あはははは。そういいながら、不便さや足りないものに対する愛着のようなものも文章からは感じます。
こだま: 20kmかけて買い物にいかなきゃいけない場所に住んでいることも、ちょっとおもしろがっているというか。くさいのも本当にイヤだけど、エッセイの仕事をもらっていた時期だったので「絶対にこれを書いてやる」と思いながら暮らしていましたし。つらいながらに、どこかおもしろがっていたんでしょうね。
──不便さの中にも発見があるというか。
こだま:入院のときもそうですし、“くせえ家”も、そのときにしか書けない文章になるだろうなと思いながら過ごしていました。
──根本的に、こだまさんは前向きな性格なんですかね。
こだま:すごく落ち込みやすい性格なのでノイローゼになることもあるんですけど、見返してやる!! って気持ちだけは大きくて。それは人に対してだけじゃなく、“くせえ家”を乗り越えるためにがんばろうとか。根本に見返したいって気持ちがあるんですよね。
──文月悠光さんとの対談で、Amazoneレビューの星1つを見て「もっといいの書くぞってなる」とお話されているのは意外でした。
こだま:「ガソリン補給」って書かれていましたけど、本当に燃料ですよね(笑)。イヤなことに出会えば出会うほどやる気がわいてくる。そういう意味で、ポジティヴなのかもしれないですね。
──逆に、日常が満たされてしまう怖さみたいなものもあるのかなって。
こだま:たぶん幸せなほうが文章を書けなくなると思いますね。幸せなことは恥ずかしいのであまり書きたくないから。そうすると何も書けなくて、結局は「不幸の渦の中」にいるしかないんじゃないかって。でもそれは自分を不幸にするので、ほどほどがいいなと。たまに不吉なことが起きればいいです(笑)。

主婦。2017年1月、実話を元にした私小説『夫のちんぽが入らない』でデビュー。 発売からいままでで13万部(2017年12月現在)を到達し、『ブクログ大賞2017』ではエッセイ・ノンフィクション部門にノミネートされる。現在『Quick Japan』、『週刊SPA!』で連載中。







