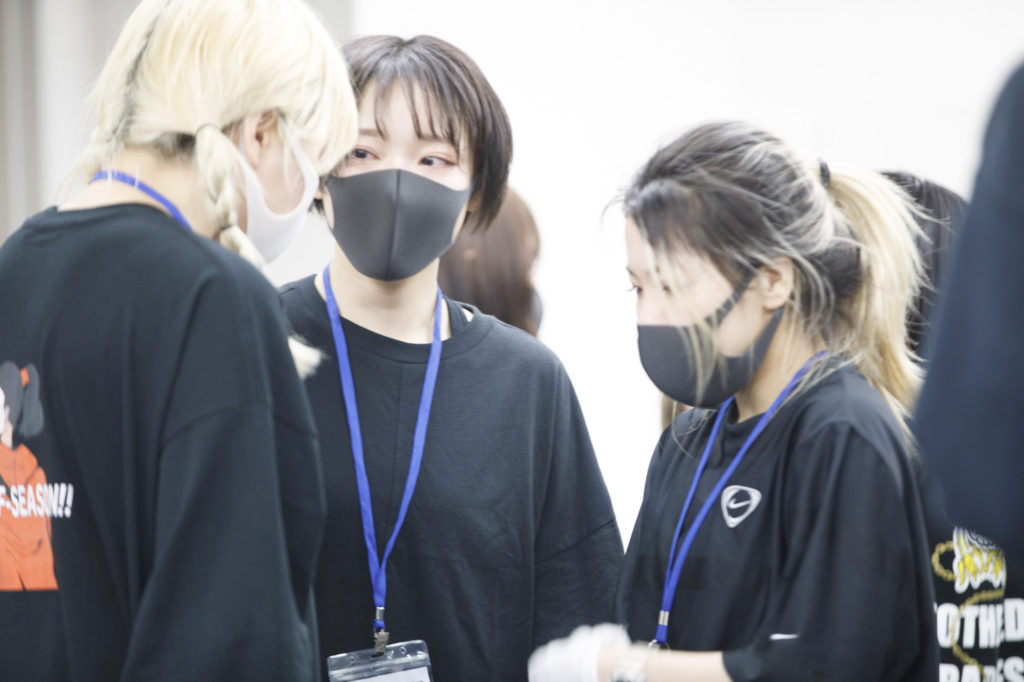1970年にPANTA(Vo.Gt)とTOSHI(per)を中心に結成されて以来、今年で結成50周年を迎える頭脳警察。昨年活動を開始した50 周年バンドには、オリジナルメンバー2人とは約40歳差の若い世代のミュージシャン、澤竜次(Gt)、宮田岳(Ba)、樋口素之助(Dr)、おおくぼけい(Key)が参加。50周年を経ても老成することなく、さらなる未来へと踏み出そうとするパッションには感服するばかりだ。
そんな頭脳警察の50周年企画ドキュメンタリー映画『zk/頭脳警察50 未来への鼓動』が、2020年7月18日(土)より、新宿K’s cinemaにて公開される。そこに映し出されているのは、システム化され数値ですべての価値が図られる現代の音楽ビジネスへのアンチテーゼであり、コンプライアンス・バカだらけの世の中で人目を気にしながら生きる我々への痛烈なメッセージだ。貴重なメンバー全員インタビュー、映画の話題のみならず、なぜ今この6人が活動を共にするのか? 志す音楽の道、そしてその先の未来を探った。
取材&文:岡本貴之
哲学的に言うと「偶然は必然なり」というね
──ようやく自粛が解除されました。6人が集まるのって久しぶりなのでは?
PANTA:それはもう、久しぶりですよ。
TOSHI:3ヶ月ぶりじゃない?
おおくぼけい(以下、おおくぼ):そうですね、レコーディング以来だと思います。
──映画を何度か通して鑑賞したんですけど、澤さんがライヴ後にPANTAさん、TOSHIさんへの愛をすごく熱く語っているところがあって。
澤竜次(以下、澤):ははははは。
PANTA:やっぱりあれがキーワードだね(笑)。
澤:予告編で1回あのシーンを見ていたんですけど、末永賢監督には「あれ、使わないでいいですよ」って言っていたんです。それで出てこないと思って観ていたら最後の方で使われていて(笑)。
──あのシーンが、6人で活動している頭脳警察の“未来への鼓動”を象徴していました。
PANTA:(宮田が澤の発言に対して)「暑苦しいんだよ!」って言うところね(笑)。あのシーンに全部食われちゃっているよね。
──PANTAさんとTOSHIさんにサポートメンバーが4人というわけじゃなくて、この6人が今の頭脳警察なわけですよね。どんな思いを持ってこのメンバーで活動していますか。
PANTA:頭脳警察は、結果的にずっと時代に沿ってやってきたから。この時点で、それぞれ出会いがあって、ちょうど再結成した1990年に生まれた世代と一緒にやることになったんだけど、それは本当に嬉しく思っています。
TOSHI:もう、みなさんを愛しています。
一同:ははははは。
PANTA:迷惑だろうけどね(笑)? ドラムの素之助は、もともと騒音寺にいて、前から一緒にやっていて。彼と同じ世代の竜次と岳は、黒猫チェルシーを休止したこともあってソロのライヴを観に行ったり芝居の音楽をやっている岳を観に行ったりしていたんです。おおくぼ君は前からアーバンギャルドやトーキョーキラーでも知っていたから、こういうメンバーで集まったのも必然かなと。まあ、哲学的に言うと「偶然は必然なり」というね。本当に自然な流れで良かったです。

映画『zk/頭脳警察50 未来への鼓動』より
──澤さん、宮田さん、樋口さん、おおくぼさんは、PANTAさんTOSHIさんに出会ったときに「いずれ、頭脳警察でやることになるかも」みたいな予感はあったんですか?
4人:いやいやいや(笑)。
PANTA:頭の片隅にもなかったんじゃない(笑)。どうだろう? 率直なところ。
樋口素之助(以下、樋口):今回は本当に偶然でした。なぜかというと、僕自体が東京にいなくてずっと京都にいたんです。京都にいてロンドンに行って帰ってきたタイミングで、たまたま50周年のときに誘っていただいて。50周年があるのは知っていたんですけど、それこそ全然違うメンバーでやると思っていたので、まったく予想してなかったです。
おおくぼ:僕はアーバンギャルドのイベントにPANTAさんに出ていただいたりしていたので、知り合ってはいたんです。きっかけは、橋本治さんが亡くなってすぐあとのラジオのときに、PANTAさんに「2人だけだとなんなんで」って呼んでいただいて、そこからいつの間にかやらせていただいている感じです。対バンはあったものの、まさか一緒に音を鳴らすことになるとは思ってなかったです。光栄です。
PANTA:今はもう、頼りにしているんですよ。まず考えもしなかったのは、この2人(澤と宮田)なんじゃないかな?
──頭脳警察と黒猫チェルシーって接点はあったんですか?
澤:1回対バンがあったんですけど。高校生のときは、70年代のロックをよく聴いていたんですけど、その中でも頭脳警察のアルバムを聴くと異質で(笑)。だからなんかもう、ほぼ架空の人たちというか、歴史の教科書を読んでいるような感じだったんですよ。
PANTA:歴史の教科書(笑)。
TOSHI:ごめん、なんか迷惑だったかな。
一同:(爆笑)
澤:いや、まさかお会いできると思っていなかったということです(笑)。だから、PANTAさんが今、「自然な流れだよね」っておっしゃっていて、自分も頷いていましたけど、それが不思議でしょうがないです。今回、映画を観て余計思いました。改めて、歴史と共に頭脳警察を観たときに、しかも50周年という節目に自分が関われているなんて、誰が想像するよっていう。
宮田岳(以下、宮田): 自分もバンドに入って一緒に音を鳴らすっていうイメージはもちろんなかったんですけど、意外と僕はTOSHIさんの周りの人たちと近かったというのがあって。
TOSHI:そうだよね。青木マリさんとか、山本久土さんとか。
宮田:なので、異端な空気の人間ではあるかもしれないです(笑)。
PANTA:今やもう大活躍で、頭脳警察と同じ日にJAGATARAもやることになっているんだから。
宮田:でも僕ら2人(澤・宮田)は、お互いが頭脳警察に呼ばれているのを知らなかったんですよ。
──それぞれ別のルートで声がかかっていたということですか。
澤:そうなんです。PANTAさんたちとスタッフさんで僕らのライヴを観に来てくれて、2回目に来たときに「じゃあ次、このメンバーで頭脳警察のスタジオに入ります」って言われたんです。それでリストを見たら「あ、がっちゃん(宮田)も誘われてたんだ!?」って知ったんです。
宮田:はっきり、頭脳警察のスタジオって聞いていなくて。
澤:PANTAさんと一緒にスタジオに入ってみたらどうか、ぐらいの感じだったんです。
宮田:そうそう。ニュープロジェクトだなって思っていたから。
PANTA:そうかあ、詐欺だな(笑)。
TOSHI:してやったりだ。
一同:ははははは。
さだまさしさんは、同じような志は少なからずあったよね
──澤さんが初めて頭脳警察を聴いたときに、異質に感じたとおっしゃいましたけど、映画を観るとやはり音楽業界の中での異質さ、特殊さを感じました。そのあたり、当のお2人はどう思っているのでしょうか。
PANTA:(身を乗り出して)いや、これが正統派なんですよ。「これが日本のロックだ」って、俺は堂々と言える。他は亜流。そんなこと言っていいのかな(笑)。
TOSHI:ははははは。
──TOSHIさんは、映画をご覧になってご自分でどのように感じましたか。
TOSHI:いや、もう恥ずかしいだけですね。ありのまま、あのまんまですよね。ただの酔っ払いだったなって(笑)。ちょっと酒を飲み過ぎていた、遊びすぎていたかなって(笑)。

映画『zk/頭脳警察50 未来への鼓動』より
──思いっきり酔っぱらっている場面もありますもんね(笑)。おおくぼさんは映画をご覧になって頭脳警察についてどう感じましたか。
おおくぼ:やっぱり、「歴史」だなって。日本語のロックを作ってきたんだなって。映画とは話が変わっちゃいますけど、去年〈NEW YEARS WORLD ROCK FES〉に出たときに、フラワートラベリンバンド(Flower Travellin’ Band with Rayとして出演)と一緒になって。PANTAさんが、「彼らはロックをやる上で、海外に行って英語でやる道を選んだけど、俺は違う道を選んだ」っていう話をされていて。その話がすごく面白かったんです。
PANTA:ちょっと長くなるんだけど、フラワートラベリンバンドって、普段の私生活から仲が良かったのね。でもこと音楽に関しては、俺はものすごく反対していたわけ。グランド・ファンク・レイルロードとかキング・クリムゾンとかレッド・ツェッペリンとか、上手く真似したからといってなんなんだよって。「何やってんの?」って俺は思っていたわけ。で、対バンライヴでフラワートラベリンバンドが後で出るときに、「モノマネ猿の大行進」って歌ったわけ。そしたら終わってから石間君(フラワートラベリンバンドのギター・石間秀樹)が楽屋に来て、「PANTA、あれはねえだろ!」って言うから、「だってその通りじゃねえかよ」って。でも石間君は、「そんな島国根性だからダメなんだよ。やっぱり英語で歌わなきゃダメなんだよ」って言うわけ。でも俺は「いや違うよ。日本人の客を前にして英語で歌ってどうするんだよ!」って言い返して。それで、彼らはカナダに行って『SATORI』(フラワートラベリンバンドの2ndアルバム)をレコーディングしたわけ。それを聴いたときに、涙が出るぐらい嬉しかったんだよ。「これが石間君が出した答えなんだな」って。
──PANTAさんの中では、日本語で自分の言葉でロックを歌うという信念が最初からあったわけですね。
PANTA:そう。本来は、頭脳警察もアメリカの誘いはあったの。それを、頭脳警察がデビューするときに、TOSHIに相談したわけ。「どうする? カリフォルニアの青い空の下でやる?」って聞いたら、「いや、日本でやるべきだろう」って。俺はその言葉を守ったんだよ。でも、夏木マリと一緒にロンドンに行ったりさ、それを勝手に破っているのがこいつ(TOSHI)なんだよ(笑)。
TOSHI:それはただのお仕事だもん(笑)。
PANTA:俺は守っているのに(笑)。アメリカに行ったときに、英語で歌うのか、それとも日本語で歌って英語の訳詞を配るのか。何が一番いいかっていうのを考えていて。今もその葛藤はあるよね。まあ、1つの回答は映画の中にも出てくるんだけど、クリミアでライヴをやったときに、「ああ、ちゃんと通じるよな」っていう確信ができたから。ただやっぱり、志の問題だなと思う。
──70年代頃は、「日本語でロックはできるか否か?」という論争が起きていた時代ですよね。そうした中で日本語で歌っているバンドがいても、サウンドを洋楽ロックにいかに近づけられるかが優先的で、さほど歌詞の内容はこだわっていないようなところもあったのではないでしょうか。
PANTA:そうだね。それに、桑田(佳祐)君にしても矢沢(永吉)にしても、みんな「た」を「ちゃ」って歌うんだよ。日本語を英語風に歌わないと恥ずかしくて歌えないの。そうじゃなくてさ、ちゃんと発音しようよっていう気持ちがあった。問題は歌う内容なんだから。まあ、桑田君なんかも過激にやってるけどね。
──ただ、直接的な言葉を使わずに、ある程度オブラートに包んでいますよね。
PANTA:それはしょうがないよ。ああいう世界でやっていたら、潰されちゃうもん。俺たちは最初から潰されていたから(笑)。ただ、桑田君なんかは、「PANTAさん、暴れるんだったらNHKだよ」って言っていて。わかるけどね。クライアントもないし、NHKでしか暴れられないんだよね。やっぱり電通の支配するメディアの中で、どうやって戦っていくかっていう、せめぎあいがむずかしいよね。ギリギリエンターテイメントの中でやっていかないといけないから。
──そういう考え方は、PANTAさんの中で時代と共に変わっていったんですか?
PANTA:時代と共に、柔軟にね。
──TOSHIさんはPANTAさんのそういう姿勢の変化は感じていますか。
TOSHI:変わってないよね。柔軟になっているのかすらわからない(笑)。「こういうことを歌うんだ」っていう、最初の69年ぐらいから言い続けてきたことは変わっていないと思う。
──映画の中では触れられていませんが、当時はフォークゲリラも盛んでしたよね。
PANTA:あんなの、ゲリラでもなんでもないけどね? 肩組んで「友よ~♫」って。
TOSHI:新宿西口で歌っていたね。
PANTA:もう、徹底的にバカにしていたからね(笑)。
──同じ日本語で歌うにしても、フォーク勢とは反目していた?
PANTA:いや、反目っていうか、相手にしてなかったから。ただ、さだまさしさんなんかは、同じような志は少なからずあったよね。「言葉を大事にしよう」っていう。そういう基本的なところに関しては。良い曲書くしね。
──意外な名前が出ましたね!
PANTA:たぶん、会って話をしたら、一番話が合うんじゃないかなって思うのが、さだまさしさんなんだよ。たぶんね? 会ったことはないけど。
TOSHI:(さだまさしも)ちゃんと日本語を大事に歌うじゃない? それは大切なことだと思う。

映画『zk/頭脳警察50 未来への鼓動』より
──他のメンバーのみなさんは、頭脳警察の曲、歌詞についてどう感じていますか? 澤さんが最初に頭脳警察を聴いたときに感じた「異質さ」の正体ってなんだったんでしょう。
澤:そうですね。自分でも「なんだろう? 頭脳警察のこの唯一無二の存在感は?」と思っていて。映画を観終わった後も考えていたんですけど、改めて頭脳警察の曲を聴いていると、本当に言葉から生まれているんですよね。新曲(「絶景かな」)もそうなんですけど、思っていることがあって言葉があって、そこに音が乗ってきているという。だからたぶん、洋楽のロックンロールとかのスタイルを、まず模倣してから言葉を乗っけるんじゃなくて、言葉が先行してそこに音が乗っている。だからリアリティがあるというのを、この映画を観て改めてすごく感じました。だから曲の聴き方も変わったというか、面白かったですね。
宮田:頭脳警察の曲は、他の人には歌えないですよね。それをまざまざと突き付けられますね。簡単にカバーできないというか。
PANTA:それと同じように、俺はポップな歌はみんなで歌えないといけないと思っているんだよね。だから、頭脳警察のロックとはまた違うところで書いたり。「ムーンライト・サーファー」(石川セリへの提供曲)とかね。
宮田:あれは衝撃的でした。俺、あの曲本当に大好きなんですよ。さっき、誰にもカバーできないと言ったんですけど、そう思いつつも、普通の人が〈子供の手術の為に 体売らなきゃならない〉(「R E D」)って叫びたくなるという気持ちも、僕も1人のお客さんとしてわかるというか。そのへんが、唯一無二なんじゃないかなって思います。
PANTA:自分たちがやりはじめたときに、お手本がいなかったんだよ。歌謡曲も演歌も、みんな否定してきたから。「冗談じゃねえ、あんなダセえ音楽やってられるか」って。だからお手本がいなくて、ず~っと手探りでやってきて、いまだに手探り(笑)。だって前にいないんだもん。いつも言うんだけど、藪の中をマチェットを使って切り開きながら、80年代に道がハイウェイになって、そこを四輪駆動で新しいミュージシャンたちが走っていくんだけど、俺たちはいまだに藪の中を手探りで歩いているっていう(笑)。良いか悪いかとかどっちが正しいとかじゃなくてね。
──その感覚がずっといまだにあるわけですか。
PANTA:だって何が正解がわからないんだもん。特にこのコロナ禍の中で。コロナが収束しても、絶対にもとには戻らないだろうし、新しいニューノーマルな世界ができてくるんだけど、ライヴのやり方にしても自分はちょっと前から、「新しい音楽の在り方ってなんなんだろう?」って考えてたから、それは1つのテーマにはなってるよね。そういう話をメンバーのみんなと話す価値があると思う。
本当に血の通った言葉が絶対的に必要
──メンバーのみなさんが会えなかった3ヶ月の間、本当に色んなことを考えたんじゃないですか?
PANTA:そうだね~。みんな考えたね。全世界が考えたよね。
──コロナによって、全世界の人々が全員並列になったような気がします。
PANTA:うん、無条件でスタートラインに立ったよね。何をやっても正解だし何もやっても間違いだしっていうのはひとつある。とにかく一歩踏み出さなきゃいけない。
──そんな中で、このタイミングで映画が世に出るというのも……。
PANTA:良いタイミングだよねえ? 瀬々敬久監督の映画(『ドキュメンタリー 頭脳警察』)の最後で、「これが俺たちの世界」って歌って、この映画の最後でいきなり2020年のコロナに行くと思ってなかったから。映画がもう終わりかなと思っていたら、2020年の渋谷が映し出されて、ライヴレコーディングをして歌ったのが「絶景かな」(新曲)。ああ、こんなに良いタイミングはないなって。だって、コロナ禍があと1年早かったら、50周年のライヴもできてなかったし、何にもできてないんだもん。2月2日の生誕祭を終えた後は、全然ライヴができなくなっちゃったんだから。本当に良いタイミングで映画が上映されることになったなって。だからなんとか色んな世代、若い世代にも観て楽しんでもらいたいね。
──頭脳警察の音楽を若い世代に知ってもらいたいという気持ちはずっとありますか。
PANTA:いやべつにそういう気持ちは特にないけど、俺たちの世代なんてろくな奴がいないから(笑)。
TOSHI:(笑)。
PANTA:やっぱり新しい世代にしっかりやってもらいたいなという思いはあるから。
──だからこそ、今の頭脳警察は世代の違うメンバーとやっているんですね。
PANTA:また、各々の活躍の場があるからね。そういうところでも広がりを持ってくれているから。それに、SNSもそうだけど、こういうWEBマガジンというのは一番重要な役割を担っていると思うし、ネットは使えるだけバンバン使って広げて行こうと思う。

映画『zk/頭脳警察50 未来への鼓動』より
──SNSには、気が重たくなるような事柄も目にしてしまうわけじゃないですか? SNSとの付き合い方はどのように思っていらっしゃいますか。
PANTA:誹謗中傷とか、何か言えば叩かれるだとか、同調圧力だよね。今度、LOFT9で同調圧力をテーマにトークをやるんだけども、その辺を俺たちはまったく無視しているから。クラスターの恐れがあるからお客さんをたくさん入れちゃいけないっていうのを無視してやっているライヴハウスもあるわけだよ。でも、それに対してああだこう言うのは、自粛を強要することになるから、それは自己責任ということになるよね。ただもし何かあったら、全ライヴハウスが非難の対象になるからね。そういうことを踏まえながらやらないと。俺たちはバグダッドにも行ったし、クリミアにも行ったけど、何かあったら自己責任でやってきたから。自己責任というよりは自己管理だよね。
──「自粛警察」なんていう言葉が生まれたりしました。
PANTA:そうだね、自粛警察VS頭脳警察なんて言葉がやたらネット上を行きかったりしててさ(笑)。
──SNSで世の中の問題を知ることができたり、それについてSNSで発信するミュージシャンの方も多いですよね。あえてそうはしないで歌や演奏にその思いを込めている、という人もいると思うのですが、みなさんはどういうスタンスでいますか。
宮田:むずかしいところではあるんですけど、基本的には表現の中でやりたいと思いますね。
だからあんまりSNSは見ないようにはしていますね。
澤:俺も見ないようにしているけど、もちろんSNSで発信することもそうしないのもどっちも正義だと思うんですよ。だから人それぞれということに尽きるとは思うんですけど、今回の自粛期間で感じたのは、ハッシュタグ1つで、世界に向けて意思表示をした気分になれるじゃないですか? 世界中が、すごく簡単になっている気がするんですよね。それで世の中を動かしていけるんじゃないかっていうある種の希望にもなっているんですけど、だからこそ本当に血の通った言葉が絶対的に必要なんだよっていうことを、音楽をやっている人とか、音に自分の意志を乗せて発信する立場の人からしたら、よりそこの気持ちが強くなっていると思います。そこを信じたいという気持ちはありますね。
宮田:竜ちゃんが、ブログで世の中のことに対して「このガイコツどもめ、くたばってしまえ」みたいなことを真っ直ぐ書いていたんですけど、僕はそれを見て、今そういうことを真っ直ぐ書いてドカーンと真正面からぶつかっている人ってなかなかいないよなって、痛快やったんですよ(笑)。
澤:ははははは(笑)。
PANTA:過激だねえ(笑)。
宮田:だから本当、とにかく大事なのは心ですよね。思いやりもそうだし。
TOSHI:やっぱりアツい男だよねえ(笑)。
PANTA:一番大事なのは、志だよね。
これだけバカにされているんだから、こんな政府なかったでしょ
──60年代、70年代はまさに志を持って権力と戦う人たちの運動があって、そこから今に至るまで、そういう権力と表立って戦うことのない時代が続いてきた結果、政治が暴走したりする今の時代になってしまいました。
TOSHI:昔でも、そんな志がある人なんて、数えるほどしかいなかったよ。あれはただのスポーツじゃないけど、ただその流れに引っ張られた人が大多数だからね。本当に志を持って活動していた人の数は知れているわけでしょ。日本人というのは、そういう運動とかは不得意なのかもね。
──最近は、デモが起こると参加する人も増えていますよね。
TOSHI:そうだね。議事堂前とかに行ってデモをしている人たちもいるけれども、集団で何かをやるというのは、国民性なのかなんなのか、日本人はあんまり得意じゃない気はしますよね。だって、これだけバカにされているんだから。こんな政府なかったでしょ。まだ田中角栄の方がかわいかったからね。今はこれだけ人を小バカにしていてさ。それで何も起こらないって、やっぱりよく教育されちゃったよね。
──権力に歯向かわないように教育されてきたということですか。
TOSHI:だって、学校教育がそうじゃない。「前へ倣え」とかさ。
──教育されちゃった、というと、80年代、90年代以降、音楽は難しいことは置いておいて楽しくエンターテイメントしようぜっていう時代もあったと思うんですよ。そうした時代に影響を受けてバンドをやっているミュージシャンの中には、どこか政治的なこと、反権力的なことを歌うことにコンプレックスがあるという人もいたんですが、今30代のメンバーのみなさんはそういう気持ちってないですか。
澤:もしコンプレックスを持っているとしたら、それを無くしていくためにあるのが音楽だと思っているので、そもそも考え方が違うのかもしれないですけど、90年生まれの僕らの世代って、あんまり流行りがないんですよね。もちろんバンドは出てきているんですけど、みんなが共通して熱狂していた音楽がなかったし、時代の流れの中で盛り上がったムーブメントもなくて。
PANTA:(生まれたのは)バブルの後だよね?
澤:そうです。バブルが崩壊したと同時に生まれたような世代です。だから、昔の音楽に触れるということが、すごく自然だったというか。親が聴いていたというのもありますし、すんなり入ってくるのはそういうものだったです。もちろん、昔の音楽を真似るとかいうことではないんですけど、でも圧倒的に大切な何かは、そこに込められていたと思うんですよ。だから、のめり込んで聴いていたんだと思うんです。
PANTA:ああ、そうか、だからジミヘンとかに行くのか。
樋口:でも、少数派だよね。僕らはそうなんですけど、一般的にはそういう方向にはいかないですよね。自分たちはガッツリ少数派っていう意識はありましたね。その時代に流行ったものじゃなくて、ビートルズとか聴いていましたね。
おおくぼ:僕は世代としてはもうちょっと上なんですけど、ロックを聴き始めたのが遅くて、それまではクラシックにどっぷりで、映画音楽とか、テクノとか言葉がない音楽ばかり聴いていましたね。
PANTA:アニメ音楽にはいかなかったんだ?
おおくぼ:行かなかったですね。どんどんコアな現代音楽の方に行ったので。でも、大学に入って演劇を始めて自分でも脚本を書くようになったんです。そうしたら言葉の大切さに気付いて、それで音楽も言葉をついているものを聴き始めて、そこで頭脳警察にも出会ったんです。
PANTA:なるほどね。
──PANTAさんは、洋楽邦楽問わず、今の音楽から刺激を受けることはありますか。
PANTA:ありますよ。「シャキーン!」(宮田がものづくりコーナーを担当しているNHK Eテレ番組)とかね。「がっちゃんのドキドキ世界」。過激だよね~、やっていることが。
宮田:ははははは(笑)。
おおくぼ:PANTAさんって、一番新しいものを知っていますよね。車に乗せていただくと、PANTAさんのDJが始まるんですよ。
樋口:そうそう。教えてもらっています。
澤:意外と僕らが追わないような、アイドルから何から。それこそ、ビリー・アイリッシュも一番にPANTAさんが仕入れて教えてもらったんですよ。
PANTA:「なんだ、欅とAKBの区別もつかねえのか!?」って(笑)。
──区別つく人の方が少ないと思いますが(笑)。
PANTA:そう? ダメだよそれじゃ(笑)。
──今日お話を伺って、この6人で頭脳警察をやっているのがとてもしっくりきました。
PANTA:本格的な活動は、この映画が終わってからだね。50周年のこの映画を撮るまでが、助走だと思うんだよ。今後の1年、2年が俺は楽しみだね。全部白紙で、何もわからないけど、色んな曲ができてくる中で、今後が楽しみです。

──最後に、映画についてそれぞれひと言ずつお願いします。
おおくぼ:是非観てほしいですし、ミュージシャンを志す人が観たら、音楽っていいな、音楽やりたいなって思ってくれると思います。
樋口:今の人にこそ、観てほしいです。昔のライヴ映像からここまでに至る歴史とか。あんな暴動みたいな今はないので(笑)。僕自身もあれを観て、「こんな世界を通ってきた人たちとやってるんだ」って思いましたし、ミュージシャンとして色んな人に観てほしいです。
澤:音楽をやっている人はもちろん、友だちとかみんなに観てほしいです。自分が関わっていることを抜きにしても、本当に楽しい映画なので。今だからこそ観てほしいですし、形に残る映画になったことがすごく嬉しいです。めっちゃ人に勧めようと思います。
宮田:僕らより下の子たちって、同世代の人たちの感覚とちょっと違うんですよ。YouTubeが生まれたときからあったりとか。そういう子たちが、好きだと思うんですよね。たぶん、ドシャーンっと痛快なものを欲している転換期だと思いますし、そういうものを求めている人に観てもらいたいです。
PANTA:たぶん、日本の戦後史を観るようなイメージになっちゃうかもしれないんだけど、ロックを好きとか嫌いじゃなくて、頭脳警察を知らなくても、とにかく楽しめますから。是非是非、新しい若い世代、高齢の方たちにもしっかり観てほしいと思っています。
TOSHI:色々カッコイイことを言おうと思って考えているんだけど、何にも出てこない(笑)。ただ、こういう70歳の人生もあるんだよって。俺個人としては恥ずかしいんだけど、何かをやるということは、どこかで恥をかくことだからね。ケツの毛まで見せる表現なんて、そんなもんだと思うから。楽しんでもらえれば。是非、笑ってください。
■作品情報
映画『zk/頭脳警察50 未来への鼓動』
結成から50周年を迎えた伝説的ロックバンド‟頭脳警察”(PANTA・TOSHI)が、新たにギター・澤竜次(黒猫チェルシー)、ベース・宮田岳(黒猫チェルシー)、ドラム・樋口素之助、キーボード・おおくぼけい(アーバンギャルド)といった若きミュージシャンを加え、‟頭脳警察50周年バンド”を始動!
”頭脳警察”と同じ時代を歩んできた者、その背中を追ってきた者、あらゆる世代の表現者の証言とともに、変わらぬ熱量を保ち続ける‟頭脳警察”の現在と過去を追うことで、日本におけるカウンターカルチャーと、サブカルチャーの歴史を浮き彫りにしていく…。
現在、新型コロナウイルス禍に揺れる日本のカルチャーシーンに、‟頭脳警察”はどのような答えを導き出すのか。PANTAとTOSHI、そして新たな強力メンバーを得た”頭脳警察”の闘いは、この時代を生き抜くための力を我々に与えてくれるに違いない!
出演:頭脳警察(PANTA、TOSHI、澤竜次、宮田岳、樋口素之助、おおくぼけい)
加藤登紀子(歌手)、植田芳暁(ミュージシャン)、岡田志郎(ミュージシャン)、山本直樹(漫画家)、仲野茂(ミュージシャン)、大槻ケンヂ(ミュージシャン)、佐渡山豊(ミュージシャン)、宮藤官九郎(脚本家)、ROLLY(ミュージシャン)、切通理作(評論家)、白井良明(ミュージシャン)、浦沢直樹(漫画家)、木村三浩(活動家)、うじきつよし(ミュージシャン)、桃山邑(演出家)、春風亭昇太(落語家)、鈴木邦男(活動家)、足立正生(映画監督)、石垣秀基(ミュージシャン)、アップアップガールズ(仮)(アイドル)、鈴木慶一(ミュージシャン)、髙嶋政宏(俳優)ほか<登場順>
監督・編集:末永賢
企画プロデュース:片嶋一貴 プロデューサー:宮城広
撮影:末永賢、宮城広 整音:臼井勝 スチール:シギー吉田、寺坂ジョニー
企画協力:田原章雄(PANTA頭脳警察オフィシャルFC)
徳田稔(TEICHIKU ENTERTAINMENT)
企画・製作プロダクション:ドッグシュガー
製作:ドッグシュガー、太秦 配給:太秦
[2020年/DCP/モノクロ・カラー/スタンダード・ビスタ/5.1ch/100分]
©2020 ZK PROJECT