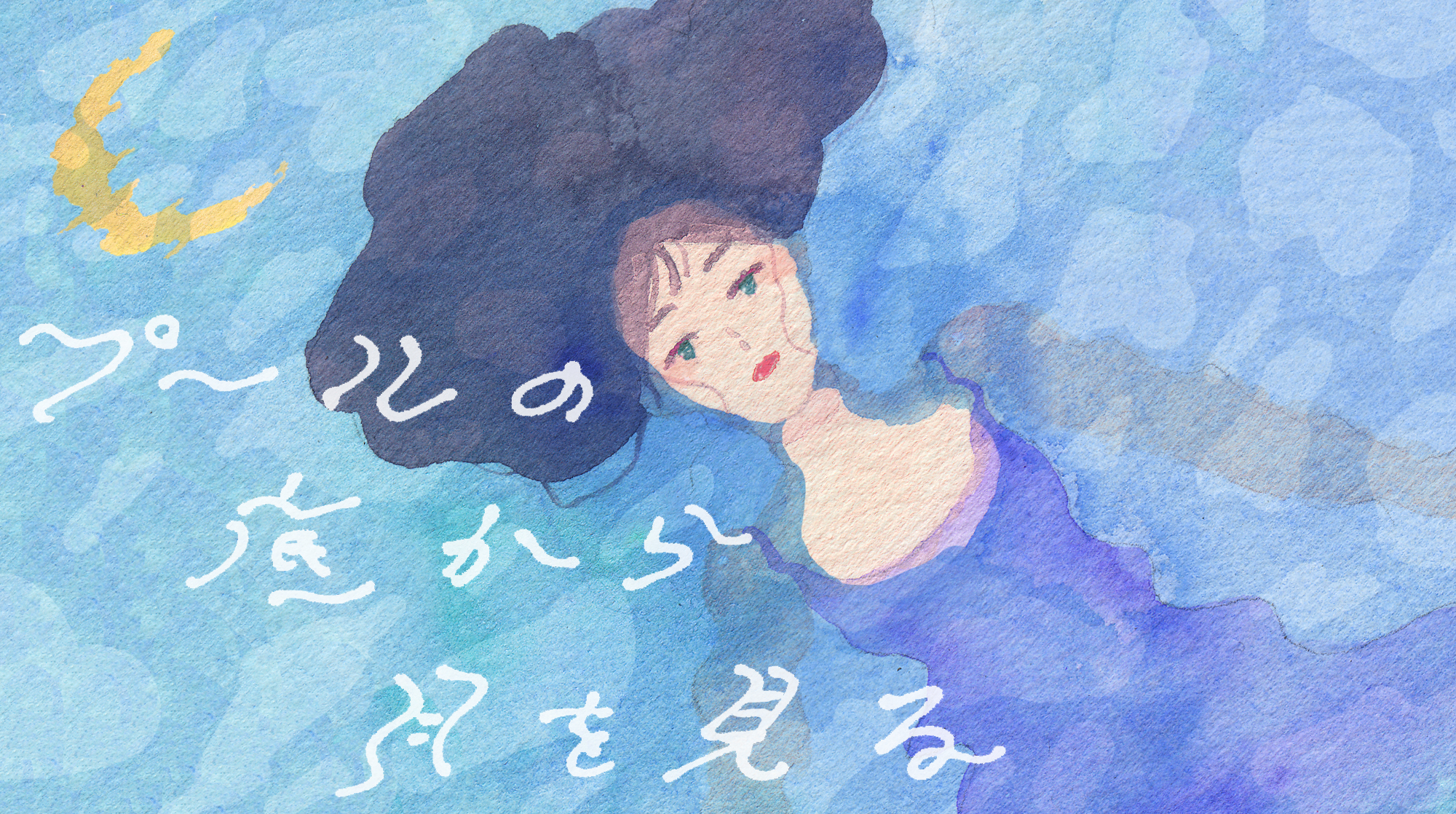
キービジュアル:いとうひでみ
「冬の匂い、暗闇で痛みは鳴るから」
先月引っ越しをした。同じ松本市内にある、大きな川の近くにあるアパートに。一年立たずに引っ越しをすることにした理由は、前の家がとにかく寒くて、2020年の冬は心身がすっかりやられてしまったから。今年はなんとしても冬が来る前に対策をしないと、と考えて、心にどっしりと埋め込まれた恐怖が原動力となり自分を動かした。
2020年の12月15日に、わたしは新宿から特急あずさに乗って移動、そして自分を追いかけるように翌日から大寒波がやってきて気温は氷点下になった。松本に来て最初に暮らした家は、東京で暮らしていたために内見もせず、サイトを見て間取りと立地の良さだけで決めた。
管理会社に鍵をもらいに行った日、「その部屋は以前店舗として利用されていて、いろいろと不備もあるので水道代を無料にします」と言われた。いろいろと不備、のあたりは気になったが、それよりも水道代が無料になるのか、という方が大きく聞こえてしまったのと、もう鍵をもらいに来ているからどうしようもない、という明るい諦めが不安を一時的に消した。
結果、大きな窓からのすきま風と、床の底冷えが笑えないくらいひどく、いくら石油ストーブを炊いても長野の本気の寒さにはぜんぜん歯が立たなかった。部屋の中でもずっとダウンを着て、靴下を何枚も履いた。常に震えていて、肩はがちがちに硬くなっていたが、そんなことにも気が付けないくらいいろいろなことに余裕がなかった。その頃は、こっちではじめたばかりの仕事もうまくいってなくて、自分が選んだはずの環境なのに思ったようにやれない不甲斐なさや、それでもあたらしい環境だから不安を出さないようにしなきゃ、とあかるく振る舞って、気持ちとのギャップを誰にも言えなかったのがつらかった。東京を離れる時に応援してくれた友人たちの顔がつぎつぎと浮かんで情けなくなった。
家に帰るとやっぱり寒いから布団をかぶるようにしてベッドでじっとしていると、そのまま動けなくなった。着替えたり、顔を洗うことを想像するだけで体に鉛がついたように重くなって、手足が動かない。それでも出かけなきゃいけないから、ストーブをがんがん炊いて、カーテンを閉め切った暗い部屋の中で体を引きずり、どうにか洗面台にたどり着く。蛇口を思い切りひねると、遠くからがちっという音が聞こえて、ガスのスイッチが入ったことがわかる。そこから10秒くらいのお湯が出るまでの時間、大量の水がただ流れていくのを見る。風呂場の蛍光灯は目に染みるような明るさで、小さな浴室は無駄に明るい。
まだ暗い時間に家を出ると、山の上には白い雪が積もっているのが見える。風が吹いて、顔が痛い。肌が出ている部分を切るような冷たい風。涙が滲んで視界がぼやける。「寒さが厳しい」という言い方がぴったりだと思った。
あたらしい環境や慣れない気候のなかで自分なりに頑張って過ごした。暗い、つらい、さむいに塗れた生活の中でも楽しいことはあったし、それが支えになって冬を越せるような気がした。寒くなったぶんだけ、景色は綺麗だった。空は透き通ったような青で、たまに降る雪は太陽に透けてきらきら光った。ぎゅうっと明るくなって燃える夕日が山の向こうに落ちていくところを何度も見た。
だけど、季節の終わりが見え始めた4月(こっちの冬は長い)、気持ちと体が限界になって今まで溜め込んでいたものが一気に溢れ出た。仕事でちょっとしたトラブルがあり、話し合いをしようという場が設けられるとわたしは壊れた機械のように泣いて、怒って、口が勝手に動き、言葉が矢のようにつぎつぎと放たれた。体が震えてどうしたらいいのかわからず、まわりの人もそれを見てどうしていいか困惑しているのが伝わってきた。自分を上から観察して、「言ってることわかるけどさ、でも結局全部自分のせいじゃん」という妙に冷静な自分の声も頭の中で聞こえた。
そこから何度も話し合いがあって、みんなが思ったことをはっきりと言うようになってきた。わたしは昔から人の機嫌を損ねることがとにかく怖くて、”思っても言わない”という方を選ぶことが多かったのだけど、自分の意見を伝えようとしないと、伝わらない、ということを学んだ。気持ちを伝えることが、少しずつ怖いことではなくなってきたし、他人は自分とちがう考え方を持っていて、理解されないこともあるという、そんなごく当たり前のことが、実感を持ってやっとわかった。わかってもらえないことは、そんなに哀しいことじゃないということも。
だけど、やっぱりそう簡単には調子を取り戻せなくて、4月はずっと泣いていた気がする。桜が咲き出した頃、実家から母と妹がお花見をしようと誘ってくれてわたしが暮らしている街にきた。ひろい公園でシートを敷いて、サンドウィッチや買ってきたお団子を広げて食べた。白い桜の花を見ながら、すこし暖かくなってきた陽気を感じていると、また勝手に涙がぼろぼろ流れて止まらなくなった。自分の意思とは関係なく、体から勝手に流れて、溢れ出す。母に顔を覗き込まれて「どうしたの?」と聞かれるが、何も答えられない。どうしてしまったのか、自分が一番わからなかった。
そのまま家まで送ってもらって、わたしはベッドに突っ伏して声を殺して泣いていた。シンクに洗い物がたまっているのを見た母が、無言でそれを片付けている音が聞こえてきて、余計にだめになって心が潰れた。
自分はどうしたのか、これからどうしたらいいのかわからない。思っていることを言葉に変換することもできず、ただ泣いている。その頃、眠ると深い井戸に落ちていく夢を見た。ものすごい重力が体にかかって、高速で落ちる。落ちながらも必死に両手を広げて、どこか掴まれるところがないか探すけど、触れるのはつめたくて分厚い壁で、見えない底までただ落ちていく。体が底にぶつかる直前でいつも目が覚めた。
時間の経過とともに少しずつ記憶は薄れていく。覚えておきたいことも、もう要らないと思っていることも、自分の意思とは関係なくどこかに消えてしまう。だけど、忘れたと思ったことが、ふいに目の前に立ち登ることもある。冬の匂いを感じた今朝、わたしは去年のことを思い出した。
また冬がやってくる。あれからしばらく時間が経って、こうしてやっと振り返ってみることができた。たぶん、わたしはあの井戸の底まで落ちてしまったのだろう。そして一番深いところまでいったから、もう上がる以外の道がなかった。
誰かの基準でつるつるに研磨された壁に杭を突き刺して、手応えを感じた方へ進んでみる。まだぜんぜん光は見えなくて、進んでいるのか後退しているのかわからない時間の中にずっといた。そんな時、側にあったのは、痛みという感覚だった。ずっと厭わしいと思って、避けてきた痛みが、自分のいる場所を示してくれた。ちがう方へ行ってしまいそうになると、大きな音をたてて鳴る。得体がしれなくて、ただ怖いものだった痛みは、暗いところでは方位磁針になった。
終わりの見えない日々はこうして、すこしずつ陸の方へ近づいて、元いた場所とはまた少し違う景色のところに着地した。
今思えば、あの頃はいろいろおかしくて、自分があんな風になるまえにできることはたくさんあったように思う。だけど、あの時のわたしには、ああする他に選択肢がなかったようにも感じる。本当の意味で、何かを”選べた”ことなんて一度でもあっただろうか。
今、一年前とは違う部屋にいて、あの日々があった意味とかを考えてる。
星野文月(ほしの・ふづき)
1993年長野県生まれ。著書に『私の証明』(百万年書房)、ZINE『Summer end』など。
Twitter:https://twitter.com/fuzukidesu1
note:https://note.com/fuzukidesu
WebShop:https://fuzukiii.theshop.jp/



