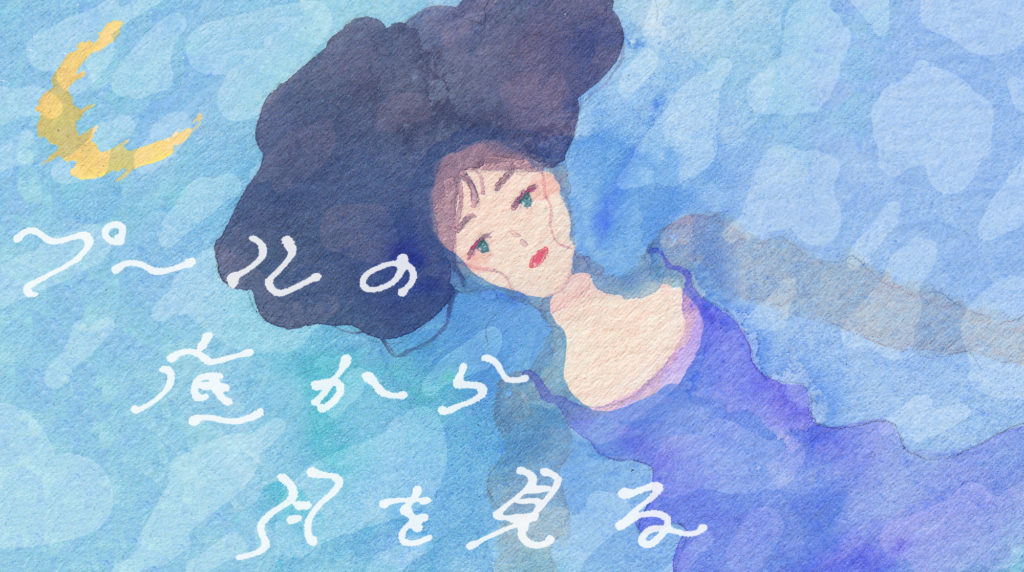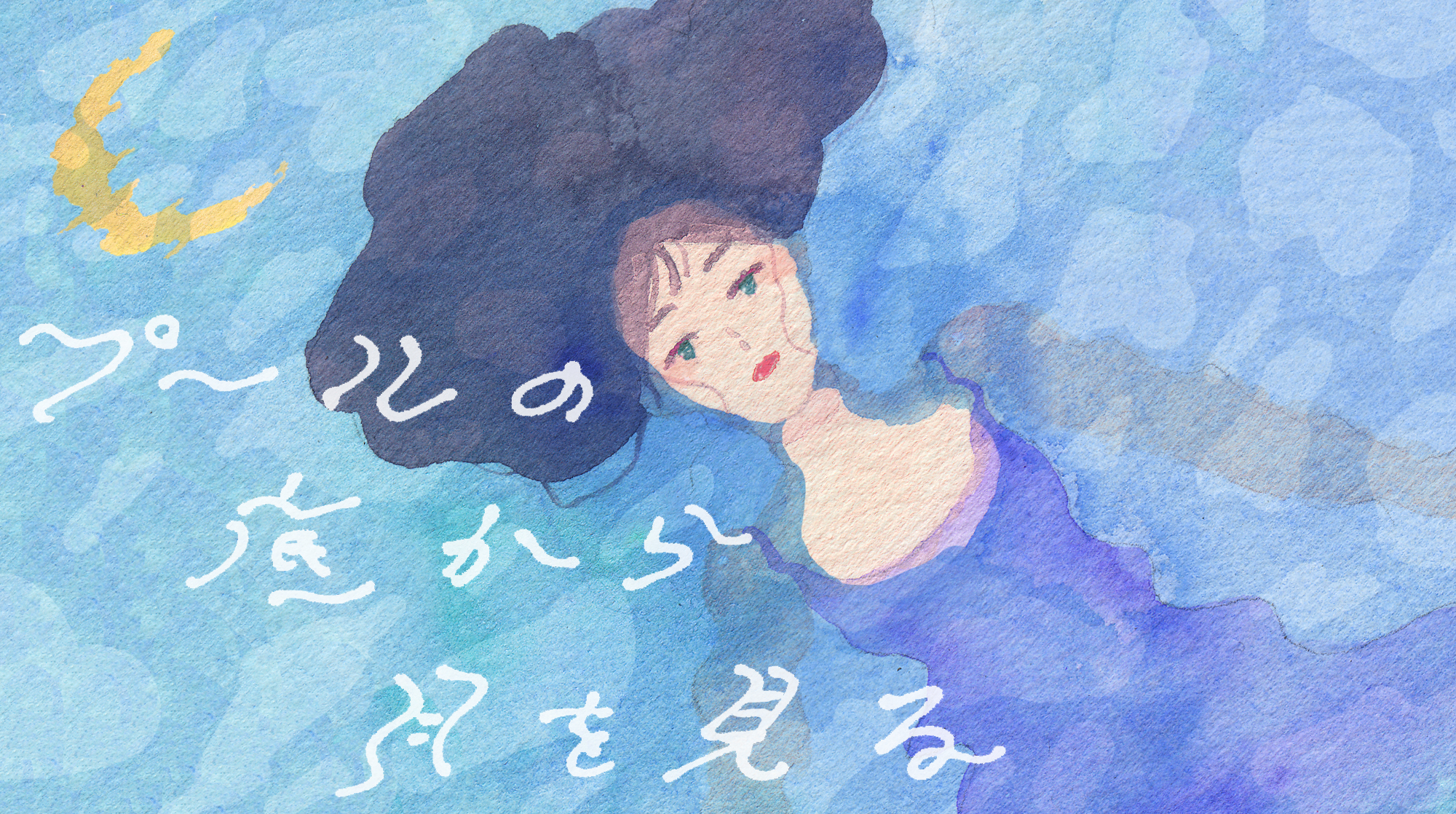
キービジュアル:いとうひでみ
「あこがれを束ねて燃やす」
2年くらい前、東京の世田谷にあるシェアハウスで暮らしていた。ある日帰宅すると同居人のあかりちゃんが、リビングで何かを燃やしているのを見た。マッチでやぐらのようなものをつくり、そこにあたらしく火をつけたマッチを焼べて、全体がゆっくりと燃えていくところをじっと見つめている。
なにか神聖な儀式を目撃したような気持ちになり、声をかけるかどうか少しためらったけれど、わたしに気づくといつもの笑顔で迎えてくれた。あかりちゃんはひとりのとき、たまにこの儀式をしているらしい。あの火をじっと見つめる瞳のなかに、一緒に暮らしていても触れることができない、たったひとりの領域を感じた。
今年は”焚き火元年”だった、とまわりの人によく話をしている。都内で暮らしていた頃も、突然、燃えている火を見たくなる衝動に駆られることがあった。だけど、火を使ってもよい場所というのは決められていて、電車で最低一時間はかかる距離にあることがわかって肩を落とした。こちらに移住してから、燃えている火を見たいという気持ちが再燃。気があう友人を誘って、近くの川やキャンプ場で何度も焚き火をした。友だちが庭から薪を調達してきてくれるので、わたしは近くにある大きな石や、小枝をせっせと拾って集める。松ぼっくりや、ススキも着火剤として使えるので取ってくる。
平日の誰もいない昼間に、火を起こして、ただそれを見る。
家の中にいると、いろいろな思考が止むことなく頭の中を駆け巡って、何かをしている最中でも別のことを考えてしまう。
だけど、森の中で火を見ていると、燃える火を見つめること以外できなくなる。
頭の中がシンプルになって、何も考えることがない、と思う。
わたしたちは、ただ黙って、薪が燃えるところを、それが時間をかけて炭になっていく様子を観察する。黒く焦げたところを見て、「炭素だ」と思う。思っても、言わないことが多い。ここにいると、伝えるべきことなんて何もないような気がしてくる。
だんだんと日が暮れて、勢いがあった火も落ち着き熾になる。炭が赤く、ぼうっと燃えている。手をかざすとあたたかい。夕闇が広がるその中で、ただ静かに燃えて灰になっていく。
火を見ていると、自分の細胞に刻まれた太古の記憶のようなものがふつふつと表出してくるのを感じる。そこから、ここまでは当たり前に地続きで、一瞬のような永遠のような時間に繋がれている。
わたしは地表の上に立ち、なぜだかすごく懐かしいような気持ちで、この火を、景色を見つめる。
音もなく火は消えて、あたりは静寂に包まれている。森の中は真っ暗で、見上げると星が一面に散らばって見える。
あの星はどれくらい遠くにあるのだろう。言葉にしなかったことは、暗闇の中に吸い込まれて、どこかに消えていく。
幼い頃、母親に「死んだら人は、星になるのよ」と教えられた。そして、見上げた空には無数の星が瞬いていて、とてもこわくなった。
お店も街頭もない帰り道をひとりで歩いているとき、本当に自分はひとりなんだ、とふと実感することがあって、それは、さみしいとか恐怖とかそういったものではなく、ただ果てしない、という感覚だった。
大人になったら、ずっと一緒に居られるような恋人や友だちができて、この気持ちはだんだん薄くなっていくかもしれない、そう考えていた10歳のときの予想は当たらなかった。
その感覚は、からだの中で芯になり、火を灯せば静かに燃えた。本当に暗いときにだけ、その明かりを感じることができる。
限られた時間が、果てしなくなるとき、わたしはわたしから解放されるのだろう。
それまで、あとどれくらいの時間が残されているのかわからないけれど、わたしがわたしであるしがらみを受け入れて、ここに立っていたい。
いろいろな場所で、いろいろな人と今年も出会った。何かが変わるわけでもない年の瀬に、なんとなくわくわくしているのは、みんなと同じ大きな船に乗っているような気持ちになれるからかもしれない。
抗えない流れに、ただ進んでゆく時間に身を預けて、来年も美しい景色をたくさん見たい。
また会えますように。
星野文月(ほしの・ふづき)
1993年長野県生まれ。著書に『私の証明』(百万年書房)、ZINE『Summer end』など。
Twitter:https://twitter.com/fuzukidesu1
note:https://note.com/fuzukidesu
WebShop:https://fuzukiii.theshop.jp/