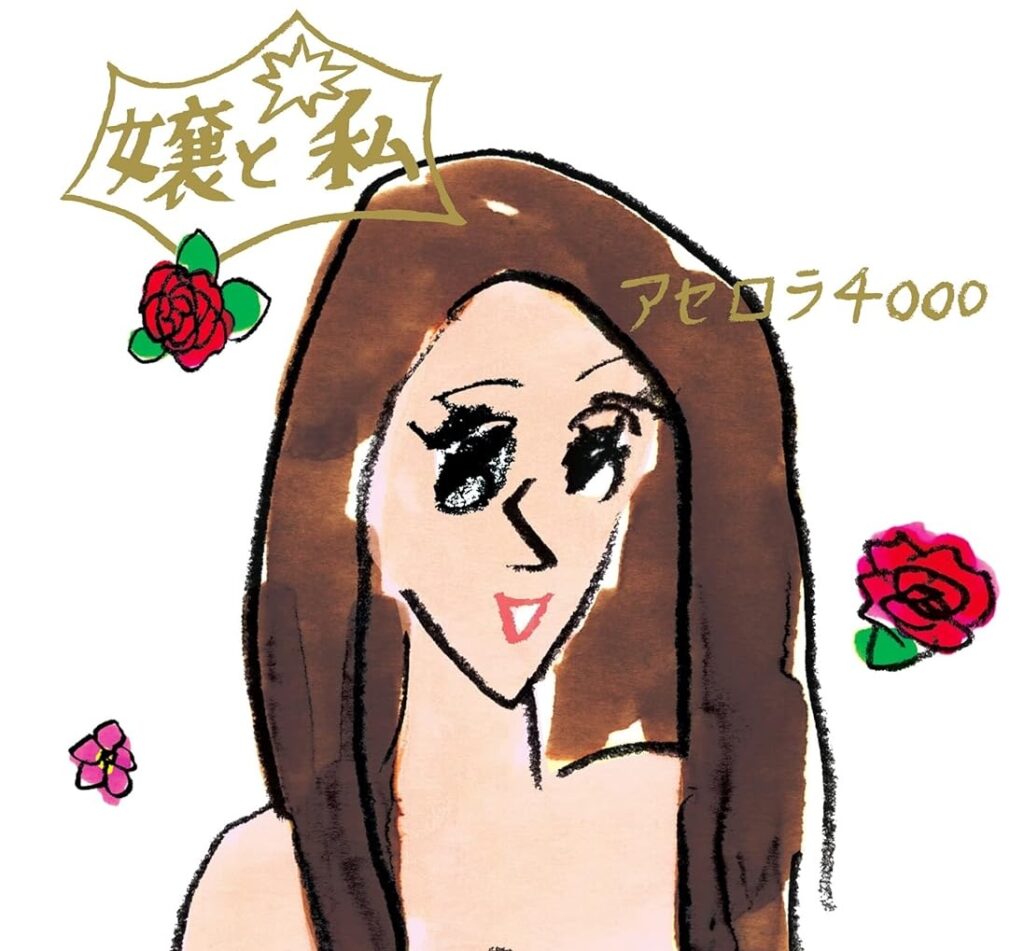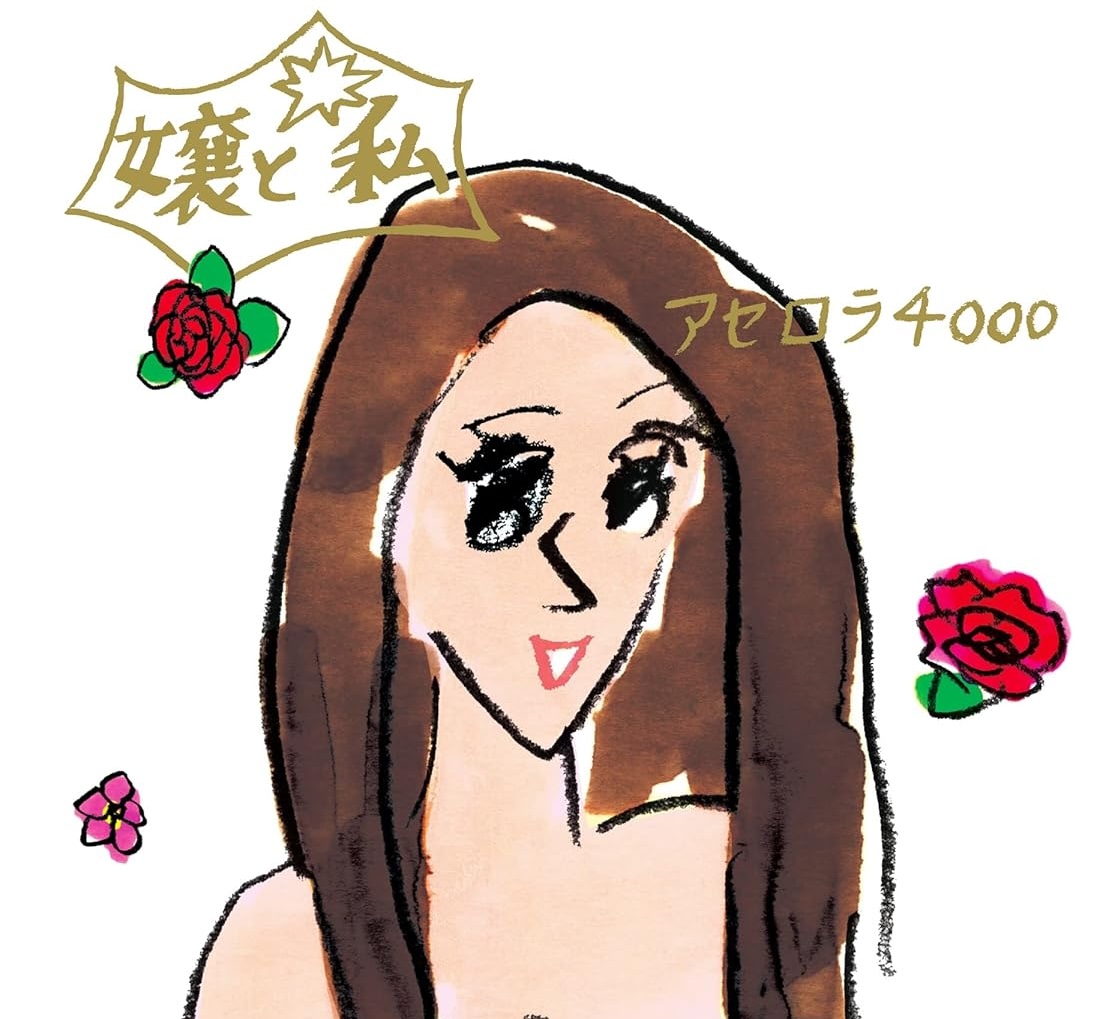
「あなた、来年結婚するわね」
私は、身を乗り出して占い師の顔を見た。ほどよく年輪を刻んだほっそりとした顔つきが、小森のおばちゃまに似ている。おばちゃまは、こちらを見ることなく親指でカチカチっと小気味良い音を鳴らすと、5色ボールペンをチェンジして、用紙に書かれた私の名前「アセロラ4000」をグルグルと赤丸で囲んだ。さらに、そこから赤い線を伸ばすと、すぐ下に書かれた女性の名前を同じように赤丸で囲んで頷いている。「間違いない」。長井秀和を彷彿とさせる自信に満ちたおばちゃまのひと言に、私は思わず息を飲んだ。
* * *
その女性と出会ったのは、2月のことだった。私は、ライターとして毎月執筆記事を掲載しているWEBサイト「らくらく娯楽ニュース」の依頼で北海道・函館の温泉ホテルに2泊3日の宿泊体験取材に行った。内容は、まだ雪深い北海道で10人ほどの記者と共に合宿を行い、体への温泉効果を測定してその結果をレポートしようというもの。「簡単に言うと、“お気楽温泉取材”です。温泉に浸かって夜は酒を飲んで美味いもん食って、いいですねえ~羨ましいですよ!」担当編集者の中邑はそう笑いながら、私の肩をバンバン叩いた。
以前の私なら、楽しそうなシチュエーションに浮かれていただろう。しかし、私ももう50歳。やっと軌道に乗ってきたライターという職業を文字通り生涯の生業とすべく、しっかりと与えられた仕事を全うしなければならない。そして、キャバクラ通いなどで働いたお金を散財することなく貯蓄に回し、都内でマンションの小さな部屋を手に入れ、そこで猫と暮らす。そんなささやかな生活を夢見ていた。恋人のテイさんとは、数年前に破局した。原因は、私にはわからない。ただ、彼女は「アセさんとは、未来が見えないでしょう」と言って私の元を去って行った。きっと、その言葉の通りだったのだろう。それ以来、私は私だけを頼りに、ただただ日々を慎ましく生きて行こうと決めていた。そんなこともあり、北海道温泉取材旅にも決して浮かれることなく、おやつは300円以内と決めて現地に向かった。
飛行機に乗って、はるばる来たぜ函館。あなたと食べたい鮭茶漬け。そうだ、函館に来たら北島三郎を聴かなければ。私はスマホを取り出した。すると、LINEの通知音が鳴った。
「みてー」
昨年取材で大阪に行ったときに出会ったキャバクラ嬢、らむちゃんからだった。彼女は、仕事を終えた安堵感とめったに来ない大阪の街にいる開放感から、日頃の節約の禁を破る欲望を抑えきれずに衝動的に入ったキャバクラにいた。20代前半で、かわいらしく、天然で、すこしドジっ子な、らむちゃん。まだ嬢としては経験が浅いようだった。
「らむ、まだ慣れてへんから、アセちゃんみたいな優しい人がお客さんでうれしいねん」。
ゆるやかな関西弁でそう言うと、私にもたれかかるらむちゃん。1時間話しただけで、すっかり意気投合した私たち。だが、時間は残酷にも2人を引き裂こうとしている。
「帰ってまうの?」
潤んだ瞳で訴えかけるらむちゃん。愛らしいタヌキ顔、長い巻き髪。ぽってりとした唇、そして巨乳。私は当然のように場内指名と延長をすると、ボトルキープすることで再会を約束して、LINEを交換して別れた。それ以来毎日のようにLINE上で逢瀬を重ねている。見ると、動画付きのメッセージだった。バレンタインデーにお店でイベントをやったそうで、フリフリの衣装で「バレンタイン・キッス」に乗って踊るらむちゃん。5秒ほどの動画で、とてつもなく癒される、心のオアシスだ。私はすぐに、かわいいね、というメッセージと愛猫のテンちゃんの動画を送り返した。らむちゃんは、猫が大好きなのだ。らむちゃんとは一度会って以来大阪には行っていないが、こうして繋がっているだけで十分満足だった。
私は、空港からバスに乗り、集合の1時間前にホテルに到着してしまった。どうやらまだ誰も来ていないようだ。団体行動が極端に苦手な私は、ほっとした。人が集まった後から輪に加わるのはハードルが高すぎる。初対面の人々で作られるヒエラルキーの頂点に立つには、一番乗りをすることにより優位性を握っておくことが大事なのだ。私は、ホテルの従業員さんに仕事で来館した旨を告げると、颯爽とホテルに足を踏みいれた。すると、ロビーには大きなリュックサックを背負った女性がポツンと座っていた。女性はこちらをチラリと見てちょこんと頭を下げた。私も、頭を下げ、改めて女性を見た。
なんだか、キレイな人だ。
化粧っ気がなくキリリとした端正な顔立ちに、黒いボブカットの髪がよく似合っている。花柄のワンピースを着た姿はとても細身で、フラミンゴのように華奢に見えた。しばしの間、立ち尽くして女性を見ていた私は、ハッと我に返った。ダメだ、ダメだ。私は仕事のためにここにやってきたのだ。それに、決めたではないか。もう恋なんてしない、と。私は女性から目をそらすとクールな態度を装い、ロビー横の売店に並んだ土産物に視線を移した。北海道の様々な美食が並んでいる。
グウゥゥ~。
お腹から、唸るような音がした。まるで高校野球甲子園大会の試合終了を告げるサイレンを真似る柳沢慎吾のような、けたたましく大きい音。しまった、朝から何も食べおらず、空腹だったのだ。チラリと見ると、女性がこちらを見ている。きっと、笑っているに違いない。赤面した私は、ポケットからスマホを取り出すと、通話しているフリをしながらいったん外に出ると、リュックからうまい棒サラミ味を取り出して一気に平らげ、お腹の虫を黙らせた。落ち着きを取り戻した私は、ホテルに戻りロビーを覗いた。女性は文庫本を取り出して読んでいる様子だった。
しばらくすると、10名ほどのメディア関係者が集まり、オリエンテーションが行われた後に、お互いに名刺交換をした。男女半々ぐらいの割合で、誰もが初対面のようだ。私が同世代のおじさん記者と挨拶を交わしている間、その背後にさきほどの女性が立っているのが見えた。私は、おじさん記者との会話を秒速で済ませると、女性と向き合った。
「はじめまして、山城です」
交換した名刺には「ライター/エディター 山城ユミ」と書いてあった。なんて、良い名前なんだ。すると、ユミさんはこちらを見てフフフとほほ笑んでいる。
「さっき、お腹が空いてたんですね。何か食べましたか?」
そう言いながら笑うユミさん。私は顔を真っ赤にして、リュックからドン・キホーテで買ったうまい棒30本セットを取り出して見せた。ユミさんは、一瞬ひるんだような表情を見せると、「美味しいですよね、それ」と言いながら会釈をして、他の人との挨拶へと向かった。私はすぐにうまい棒をしまった。ユミさんを目で追うと、外国人記者と英語で会話しているではないか。英語ができるなんて、すごい。それに、外国からも取材に来てるのか。私は気を引き締め直して、オリエンテーションに向かった。
合宿は、まったく想像と違っていて、初日からビリーズブートキャンプばりの厳しいプログラムが組まれていた。早朝のエクササイズにはじまり、ウォーキングして、座禅を組んで瞑想を行い、ヒップホップダンスをして汗をかき、ようやく温泉に入ると、入浴後すぐに卓球の試合が行われた。中年太りで90キロもの体重を抱えた私には、そのどれもがしんどく、まるで拷問のようだった。ホテルの会議室で、ラジカセから流れるヒップホップに合わせて無様に手足をばたつかせる私。どこがお気楽温泉取材なんだ。完全にだまされた。私は、編集者・中邑の顔を思い浮かべ恨みつつも、よくわからない最近の若者のラップに合わせて、自分なりのダンスを踊った。その様子を、芸人のですよ。に似たダンス講師が見ている。講師は何も言わずに、私の背後を見て言った。
「あなた、素晴らしいですね! ダンスやってるんですか?」
後ろを見ると、ユミさんが踊っていた。しなやかな手足の動き、所作がいちいち美しい。
「ええ、学生時代にちょっと」
はにかみながらもそう応えるユミさん。少しも息が乱れていない。皆が、羨望の眼差しを向けている。一方、疲れ果てウシガエルのようにうつ伏せに倒れて息も絶え絶えの私。その姿をユミさんが無表情で見下ろしている。なんて、恥ずかしいんだ。できれば私も華麗に踊りたい。だが、体がまったく動けない。倒れたままの私を見た講師が、こう言った。
「ちょっとちょっと! ボブ・サップに負けたときの曙じゃないんだから!」
一瞬、静まり返る会議室。3秒ほど経っただろうか。ユミさんが、「プッ」と吹き出した。それを合図に、ドッと笑うオーディエンス。同世代らしき女性新聞記者も、おじさん編集者も、手を叩きながらこちらを見て爆笑している。そんなに面白いかというと、まったく面白くない。第一、話題が古すぎる。その証拠に、20代らしきメガネっ子女子ライターはキョトンとしているではないか。会心の一撃を放ったかのようなドヤ顔で立っている講師。私は、あまりの惨めさに腹も立たなかった。講師が私の腕を引きながら体を起こす。
「大丈夫。あなたもきっと、変われますよ。さあ、踊りましょう!」
1人、激しく踊り出す講師。かつての私だったら、不貞腐れて帰っていたかもしれない。だが、私ももう50歳。さすがに団体行動が苦手だなどとは言っていられない。ましてや、これは仕事だ。ガムシャラにがんばらなければ。私は思い直し、体を懸命に動かして、踊った。
一日のプログラムを終えると、夕食までの間、自由時間となった。私は部屋に戻り、ベッドに横になって疲れを癒した。あまりにも疲れてしまい温泉に入るどころではない。目を閉じると、こちらを見て「プッ」と吹き出すユミさんの顔が浮かんでくる。なんという屈辱。だが、笑われてもしょうがない。怠惰な生活を送り続けてきた結果の無残なメタボ体形。私はTシャツの裾からはみ出たお腹を右手でポンポンと叩きながら天井の染みをジッと眺めていた。寝返りを打ちスマホを見ると、LINEが1つ来ている。らむちゃんからだ。
「ねこ、かわいい✨」
私は、かわいいよね、と返信して、少し眠った。
アセロラ4000『嬢と私』夢を見ていたらおじさんになっていた〜はほぼ毎週木曜日更新です。
次回更新をお楽しみにお待ちください。
月に一度のキャバクラ通いを糧に日々を送る派遣社員。嬢とのLINE、同伴についてTwitterに綴ることを無上の喜びとしている。未婚。
https://twitter.com/ace_ace_4000